|
TOYOTA COMS �O�� �������G���W���o�R�Ńm�[�t���[���̏ꍇ���������N���b�N���Ă��������B |
|

|
|
|
���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ����A���B�ɂ� microcars �Ƃ����J�e�S���[�������āA�e�������̋K�i�̈Ⴂ�͂��邪�A�T�ˈȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B �E�V�[�g�̓h���C�o�[����я�q�P�l (���v��l) ���� microcars �͑����̍� (�h�C�c�A�t�����X�A�C�^���A�A�I�[�X�g���A�A�X�y�C��) �ŃI�[�g�o microcars �̎�v���Y���̓t�����X�ƃC�^���A�ł���A�C�^���A�̏ꍇ�͊ȒP�ȍu�K�Ǝ�����14����^�]���ł��邱�Ƃ���ŋ߂͎�N�҂̃��[�U�[�������Ă��āA�X�^�C������ҍD�݂̂������Ȃ��̂������Ă���B�Q�l�ɑ�\�I�� microcars �Ƃ��ăt�����X�� Ligier (���W�F) �̎ʐ^���f���Ă����B �����Řb�����{�Ɉڂ��ƁA���{�ŕ��ʎԂ����������K�i�̃N���}�Ƃ����Όy�����Ԃ����A����3���1��͌y�����ԂƂ������Ƀ��W���[�ɂȂ�A�������\���ɍL�����������ʎԂƑ��F�̂Ȃ����m���嗬�ƂȂ��Ă���悤�ȏ����A�����m�̂悤�ɍ��̌y�����Ԃ͕����������邱�ƂƔr�C�ʂ����������邱�Ƃō�����p�ԂƂȂ��Ă���B������O���[�o���ȖڂŌ���A���B��A �Z�O�����g�ƌĂ��J�e�S���[�ɂ���ɂ̓T�C�Y���r�C�ʂ����Ə����T�C�Y�A�b�v����A�\���ɐ��E�헪�ԂƂ��ĉ��B�݂̂Ȃ炸�A�W�A�̐V�����ɂ��̘H���ł���A�Ƃ����b�͍��X�����܂ł��Ȃ������̊W�҂������Ă��邱�Ƃ��B �b�͕ς���č��̓��{�ł��y�����Ԃ����X�ɏ������A�����Ă݂�Όy�ƃo�C�N�̒��ԓI�ȃN���}�ŁA�O�q�̉��B�� microcars �̍ŏ����f���ɋ߂����̂����݂��Ă���B�r�C�� 0.5L (50cc) �ȉ��܂��͒�i�o�� 0.6kw �ȉ��̎ԗ��͓��H�^���ԗ��@�ł͌����@�t�����]�� (�ʏ̌��t) �̈����ɂȂ�B���t�̑傫���͕ۈ���Œ���2.5m�A��1.3m�A����2.0m ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƋK�肳��Ă��邩��A�����̋K�i�������4�֎ԂƂ����ǂ� ”���t” �ƂȂ�B ����ł͌��t�Ƌ��ʼn^�]�ł��邩�Ƃ����A���H��ʖ@ (����@) �ł͕��ʎ����ԉ^�]�Ƌ� (���ʖƋ�) ���K�v�ƋK�肳��Ă���B����@�ł͕��ʎԂƂ����Ƃ�2�ւ̌��t�̂悤�Ƀw�����b�g�̒��p���i�K�E�܂̋`�����Ȃ��A�@�葬�x�����t�� 30�q/h ����60�q/h�ɃA�b�v�����B�Ȃ������̃N���}�̓~�j�J�[�ƒ�`����Ă��ĕ��ʎԂƂ͂����������H�⎩���Ԑ�p���H�̑��s�͏o���Ȃ��B���������{�̃}�j�A�̊ԂŃ~�j�J�[�Ƃ����ƁA1/43�Ƃ�1/18�̃X�P�[�����f�����Ӗ����邽�߈�ʓI�ɂ̓}�C�N���J�[�ƌĂ�Ă���̂ŁA���̎���L�ł��}�C�N���J�[�Ƃ����ď̂��g�p����B�������A������܂��O�o�̉��B�� microcars �ƍ�������₷�����d�d�B �����ň�t��������ƁA�s�U�̑�z�ȂǂŎg���Ă��鉮���̕t����3�֎Ԃ͕��ʖƋ����K�v���Ƃ����ƁA���͓���@�ł͑����{�����Ƃ����`�ŗ�O�K�肪�݂�����Ƃ���Ă��āA����͍����ɂ��Ǝ��� (�v����Ƀz�C�[���x�[�X) ��0.5m �ȉ��ŎԎ�������Ȃ�3�֎Ԃ͌��t�Ƌ��ʼn^�]�ł���Ƃ������ƂŁA�s�U���̑�z3�֎ԂȂǂ͖ڏo�x�����`�����Ƌ���OK�ƂȂ�킯���B
�������A���̃V�j�A�[�J�[�Ƃ����̂͌��邩��Ɋ댯�ȏ�ʂ�ڂɂ��邱�Ƃ������A��Ԃɖ����Ŏԓ��𑖂��Ă�����A�Ԉ֎q���Ƃ���X�[�p�[�̓X���𑖂��Ă��Ċ낤���ڐG���ꂻ���ɂȂ�����ƁA����Ŏ��̂͋N����Ȃ��̂��Ǝv���Ē��ׂĂ݂���A2012�N�x�܂ł�5�N�Ԃ�91���������A���̂������S���̂�33���������Ƃ������Ƃ������B���̃V�j�A�[�J�[�ɂ��Ă͍��ڂ����߂� (���ʕ҂�) �����悤�Ǝv���Ă���B �O�u���������Ȃ������A����̎���Ԃ̓g���^ �R���X (COMS) �ł���A�������������t�o�^�����^�]�ɂ͕��ʖƋ��̕K�v�ȃ}�C�N���J�[�ł���B���Y�̃}�C�N���J�[�Ƃ����Α�ւȂǂŃ}�j�A�̊Ԃł��L���Ȍ��������Ԃ��������Ă������A���ɂ���͐��Y���I�����Ă����B���ɍ��Y�ԂȖ����̂��ȊO�ɂ��Q�`�R�������Ă���悤����������C�O����̗A���i�ŁA���̒����獡��͒�������̗A���i�������p�ɉ������Ĕ̔����Ă��� ACCESS �Ƃ�����Ђ̃~�j Ace �����グ�Ă݂��B  
�����R�Ԃ̏������r������� 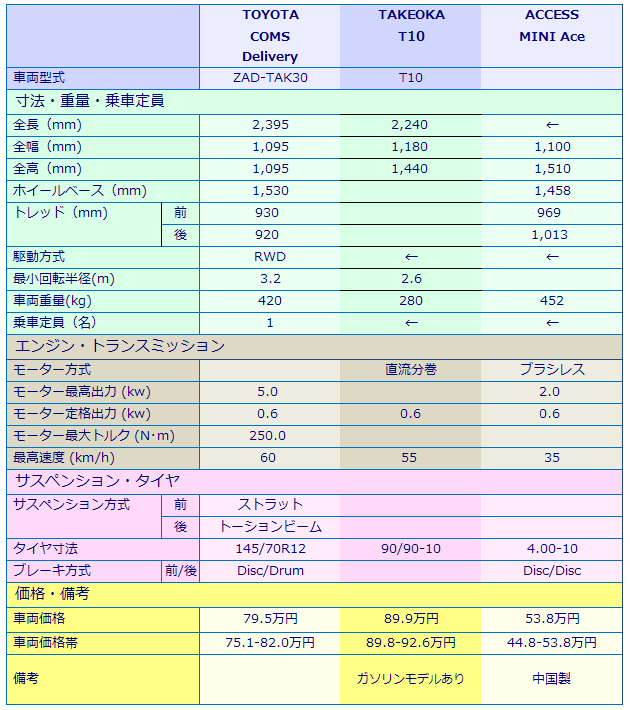
�������̃~�j Ace �͐��\�I�ɂ����悤�����A���i���R�Ԃł͈�Ԉ����BT10 �ɂ��Ă̓R���X�Ƃقړ����̃X�y�b�N������Ă��邪�A���i��10���~�������ݒ�ɂȂ��Ă���B���̓R���X�̓g���^�Ƃ͂����Ă����ۂ̊J�����������g���^�ԑ̂ł���A���� OEM �Ƃ������ƂɂȂ�B�ܘ_�g���^�ԑ̂����Đ��Ԉ�ʂ��猾���Ώ\���ȑ��Ƃł���A���Ƃ̎���I�ȃ��m���������̎�̃N���}�ɂ����Ă͗�O�I�Ƃ����B �R���X�̃o���G�[�V�����͑傫�������ď�p�� P-COM (82���~) �Ɖݕ��p�� B-COM ������AB-COM �ɂ̓f���o���[ (79.5���~) �A�f�b�L (75.2���~) �A�x�[�V�b�N (68.7���~) ��3�O���[�h������B�����̈�Ԃ̈Ⴂ�̓��A�̃��b�Q�[�W�X�y�[�X�ł���A���h�ȃN���[�Y�ƃG���A�����f���o���[�A�����̖����ב�����f�b�L�A�����ĉב�炵�����m�̖����x�[�V�b�N�A����ɂ͍����̒Ⴂ�g�����N������p�Ԏd�l�� P-COM �̈Ⴂ������B 
�Ȃ��ȉ��̎ʐ^�͑S�ăf���o���[���g�p���Ă���B�G�N�X�e���A�͑O�q��T10��~�j Ace �ɔ�ւ�Βi�Ⴂ�ɍC�����Ă��邵�A���Y�ݔ��ɋ����|�����Ǝv���悤�Ȋ��炩�ȃJ�[�u��`���Ă���B���̓R���X�������������ɂ�80���~���o���Ă��ꂩ��A�Ǝv�������A�������Ă݂���̕���ł͏\���ɗ��h�Ȃ̂�������Ȃ��B  
����Ŏ����͂Ƃ����A�O�q�̂悤�Ƀh�A�͖������炻�̂܂܂ŃL���r���͊ی����ƂȂ�B�V�[�g�\��̓��[�J�[�T�C�h�ł̓��U�[�ƌ����Ă��邪�A��������U�[�Ƃ����ɂ͂��܂�ɂ��p�����������̃r�j�[���ŁA����ł������Ă݂�Ƒ����ɃN�b�V�����͂���B�V�[�g�����͖ܘ_�蓮�������A�������ł��邾���}�V���B�������A�㉺�̒���������悤�ȃ��o�[�̗ނ͌�������Ȃ����瑽���o���Ȃ��̂��낤�B |
|
|
�C���p�l�A�Ȃ�Č�������C���p�l�ɓ{��ꂻ���Ȃ��炢�ɃV���v���ȃp�l���̒����ɂ́A�ꉞ���[�^�[�N���[�X�^�[������A���̒��ɂ͉t�����[�^�[������B����ȊO�ł̓I�[�f�B�I��G�A�E�R���炵�����̂���������Ȃ��B����A�G�A�E�R���Ȃ���ґ�͌���Ȃ����A���߂Ēg�[���炢�͗~�������g���^�ԑ̂̃T�C�g�Œ��ׂĂ݂���A�����̓I�v�V�����ɂ��Ȃ��悤���B�l���Ă݂����͌��t���Ȃ̂�����A�G�A�E�R�����I�[�f�B�I�������ē�����O�������B 
���O���͉��������A����ł͊̐S�̑���͂ǂ��Ȃ̂��낤���H ���̑���ɂ��Ă͌�҂ɂāB |
|


 �R���X�͑S�Ẵo���G�[�V�����Ńh�A�������Ă��Ȃ����߂Ƀh���C�o�[�͌����Ă݂�ΐ������N�������A�܂����t���ł�����d�d�B���������Ӗ��Ńf���o���[�̃��b�Q�[�W�G���A�͂܂Ƃ��ɃN���[�Y�h�ƂȂ��Ă��ĉJ���𗽂���B��̏ꏊ�ł�����B���̏��ʂ������グ��ƍX�ɃX�y�[�X������B���̏��͋ߏ��� DOIT �Őؒf���Ă�������Ƀ}�W�b�N�e�[�v��\�����悤�ȍ�肾�B�܂����Y�䐔���l����A�g���^�u�����h�Ƃ͂�������ʎ���I�ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�B�Ȃ��A���A�Q�[�g�͈ӊO�ɃV�b�J���ł��Ă��āA���̂��炢�̕i���̃h�A���^�]�Ȃɂ���������d�d�Ȃ�Ďv���Ƃ��낾�B
�R���X�͑S�Ẵo���G�[�V�����Ńh�A�������Ă��Ȃ����߂Ƀh���C�o�[�͌����Ă݂�ΐ������N�������A�܂����t���ł�����d�d�B���������Ӗ��Ńf���o���[�̃��b�Q�[�W�G���A�͂܂Ƃ��ɃN���[�Y�h�ƂȂ��Ă��ĉJ���𗽂���B��̏ꏊ�ł�����B���̏��ʂ������グ��ƍX�ɃX�y�[�X������B���̏��͋ߏ��� DOIT �Őؒf���Ă�������Ƀ}�W�b�N�e�[�v��\�����悤�ȍ�肾�B�܂����Y�䐔���l����A�g���^�u�����h�Ƃ͂�������ʎ���I�ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�B�Ȃ��A���A�Q�[�g�͈ӊO�ɃV�b�J���ł��Ă��āA���̂��炢�̕i���̃h�A���^�]�Ȃɂ���������d�d�Ȃ�Ďv���Ƃ��낾�B
